| 編集長コラム | ||
江刺しの稲を育てるために | 農業経営者 5月号 | (1993/05/01)
かつて、水路に植えた稲は年貢や小作料の対象とはならず、取れた米は作った人のものになったのだという。どこの農村にもあったであろう「江刺しの稲」も、今や水路がコンクリートになり、またそんな手間のかかる作業をする人もいなくなり、いつの間にか目に触れることもなくなってしまったのだろう。
植えてあったのは収穫一週間前のコシヒカリだった。畦の内側の稲では分げつが20本前後、穂の粒数が110粒くらいなのに対して、江刺しの稲では分げつが30本以上あり、位数も140粒くらいもあるのだ。すでに収穫の終わっている加賀ヒカリの株を引き抜いてみると、付いてくる土の塊が断然大きく、根の勢いの違いを感じる。
江刺しの稲は、気がつけば草を取るくらいで、水路では水管理のしようもない。肥料や農薬は流れてくるだけ、もちろん耕起もしない。移植も、田植え時では水が深すぎるので一旦水田内に仮植して大きくなってから植え直すのだそうだ。自然のままということではないが、いってみれば放ったらかして育った稲である。
畦の内と外だから元々の地力の差にそんな違いがあるはずもない。にもかかわらず、素人の僕にもハッキリ見える違いなのだ。採光や風通しがよいことから出来の良い畦際の稲と同じ理屈と思う方もいるかもしれないが、江刺しの稲と比較したのはその畦際の稲なのだ。それでこの差なのである。この違いを何と説明すべきなのだろう。
いってみれば放ったらかしにされ、言葉は悪いが、継子抜いにされていた稲が手間をかけお金をかけて育てたはずの稲よりもはるかに立派に育っているのだ。
農業が土や作物という「自然」の持つ潜在的生産力を人間の都合に合わせて引き出すための方法であるのだとしたら、そこで行われている「技術」や「経営」とは、何と不確かで頼り甲斐のないものなのであろうか。むしろ、良いと思ってしていることが、かえってその可能性を押し殺していることすらあるのではないか。
僕は無農薬農業論者でも有機農業論者でもない。しかし、土を耕すつもりが田を踏み固め、有機物の還元がないからこそ地力が衰え、その結果多肥に傾き、作物が弱くなるからますます農薬・除草剤への依存度を高め、そして土はますます生命性を乏しくしていく。またいつしか省力が手抜きに変質していく。そしてその悪循環が経営を、農業を滅ぼしていくことにつながるのではないか。
それは、自然の摂理との整合性を考慮に入れた「循環の農法」を無視し、ただ現代的技術手段を無疑問に取り込んで行く我われの技術観、あるいは目先の儲けや手間が減ることばかりに気を取られその過程で失われていくものの大きさに気づかないでいる功利主義的経営観の中にその原因があるような気がする。
人は「経営の永続性」を語り、またそれを望む。しかし、人というものは多分、自覚的にそれを問わぬ限り、いつの間にかその落とし穴に落ち込んでいく存在なのであろう。
もし僕たちが経営者だというのであれば、この江刺しの稲を水田の内側に育てること-その作柄だけでなく経営の中身においても-を自らに問いかける責任を持っているのではないか。
今日の作柄や利益の多少に一喜一憂するのはもうやめにしよう。少なくとも、あの江刺しの稲のようにもっと大きな可能性が我われには与えられているからだ。
次号より、稲作に限らず、いわばこの江刺しの稲を畦の内側に作る人々、またそれに近づける技術や経営への取り組みを、小さな自営業者の自らへの練習問題として考え、報告して行きたい。




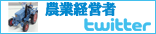



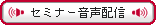



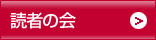

chat free dating site
free phone chat lines