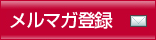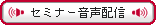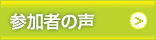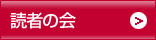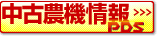農業経営者取材 [75]
- 新・農業経営者ルポ [47]
- スーパー読者の経営力が選ぶ あの商品この技術 [28]
- 叶芳和が尋ねる「新世代の挑戦」 [13]
農業経営者コラム [51]
- 激突対談・高橋がなり×木内博一 [1]
- 高橋がなりのアグリの猫 [26]
- ヒール宮井の憎まれ口通信 [14]
- 木内博一の和のマネジメントと郷の精神 [7]
- 幸せを見える化する農業ビジネス [5]
提言 [60]
- 視点 [60]
農業技術 [68]
- 大規模輪作営農のための乾田直播技術 [6]
- “Made by Japanese”による南米でのコメ作り [6]
- 乾田直播による水田経営革新 [23]
- 防除LABO [31]
農業機械 [23]
- 土を考える会 [1]
- 機械屋トラクタ目利き塾 [16]
- 機械屋メンテ塾 [6]
- 機械屋インプルメント目利き塾 [2]
農業商品 [8]
- 読者の資料請求ランキング [8]
時流 [287]
海外情報 [3]
- 『農業経営者』の休刊とWeb化に関するお知らせ (08/04)
- 夏期休業期間のお知らせ (07/26)
- 年末年始休業のお知らせ (12/23)
- 夏期休業期間のお知らせ (07/28)
- 夏期休業期間のお知らせ (08/10)
HOME >2006年12月
| 特集 | ||
あなたの「退き際」、しっかり見つめていますか?
農業経営から撤退する自由 | 農業経営者 12月号 | (2006/12/01)
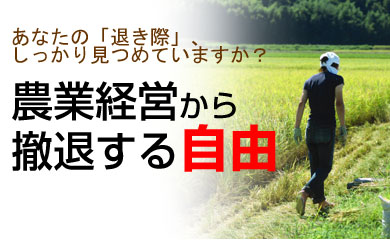
「引退」そして「撤退」—。これらの言葉に、農業経営者であるあなたは どんな印象を持つのだろうか。農業の世界では「離農」を語ることが、 一種のタブーとして受け取られてきたようにも思う。 しかし、経営における合理的な判断の選択肢として撤退すること、 新たな人生を目指して引退することは、決して否定されるべきものではない。 農業を取り巻く環境が激動な時代だからこそ、離農という 「経営者の勇気ある決断」について、率直に考えてみようではないか。
撤退・引退は経営者が自ら考えよ
日本農業に地すべり的な変化が起きている。その変化は本誌が目指す農業の産業化に向かう変化である。同時にその変化は、農業からの撤退を余儀なくされる者も生み出す。
創刊号以来の読者が、“離農”を理由に購読中止のご連絡をいただくことが増えている。本誌は職業あるいは事業として農業を選び、それにチャレンジする人々を対象とする雑誌である。そんな雑誌をご購読いただいた方々が離農される。そのご報告を特別の想いで聞かせていただいている。
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
第31回 農業と土木業、ふたつの経営を極める | 農業経営者 12月号 | (2006/12/01)
【(有)フラワーうさ代表取締役 (有)宇佐重機代表取締役 菅原維範 (大分県宇佐市)】
 数年前から建設業による農業参入が盛んだ。公共事業が減少するなか、従業員の仕事先を確保したいと参入した企業も少なくないが、成功事例は多くなく、参入には賛否両論がある。今回登場する菅原維範氏は農業から土木に転身し、再び農業に参入した人物。土木と農業の魅力を的確に捉え、相乗効果も上げている。一度外に出たからこそできる農業経営がある。
数年前から建設業による農業参入が盛んだ。公共事業が減少するなか、従業員の仕事先を確保したいと参入した企業も少なくないが、成功事例は多くなく、参入には賛否両論がある。今回登場する菅原維範氏は農業から土木に転身し、再び農業に参入した人物。土木と農業の魅力を的確に捉え、相乗効果も上げている。一度外に出たからこそできる農業経営がある。
「花はいつもオレのほうを向いて微笑んでくれる。女性はそうはいかんけどな(笑)」―自分が育てるパンジーを手にとって菅原維範さん(60)は話す。花に向けるやさしいまなざしからは、“花一筋”というイメージが伝わってくる。しかし花との出会いはさほど古くない。
いったん就農したものの、27歳で建設会社を設立。以来、土木の世界に身を置いてきた。そして50歳を過ぎ、再び農業に足を踏み入れたという異色の農業経営者である (以下つづく)
| 農業経営者取材 | スーパー読者の経営力が選ぶ あの商品この技術 | ||
岐阜県大垣市上石津町 高木正美 氏が選んだ商品 | 農業経営者 12月号 | (2006/12/01)
- ライスショック(大きな国で)
- 何がどうおいしいを数字ではっきりと(花総果菜)
- 農業起業講座。(ほぼ日刊三浦タカヒロ。)
- 広島で屋上緑化かるいちばんとカルベラの展示です♪♪♪(Urban Green Life 街にもっと緑を・・・ 兼定興産の屋上緑化土「かるいちばん」)




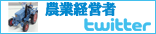

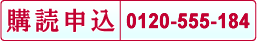
 コメの販売で大きな利益を見込めない情勢の中、支出を圧縮することで利益率を向上することも重要である。農機のセルフメンテナンスや自作アイテムの導入でコストダウンを徹底し、中山間地の特徴に適合した経営スタイルの確立を目指す。
コメの販売で大きな利益を見込めない情勢の中、支出を圧縮することで利益率を向上することも重要である。農機のセルフメンテナンスや自作アイテムの導入でコストダウンを徹底し、中山間地の特徴に適合した経営スタイルの確立を目指す。