| 編集長コラム | ||
規模拡大を望むなら深く耕せ | 農業経営者 9月号 | (1994/09/01)
前月のこの欄で「不耕起」を取り上げたら、話題のヒントをいただいた茨城県牛久市の高松永さんから、
「省力、低コスト化のための不耕起だと言うなら、机上で考えるような見当違いの『省力-低コスト論』に惑わされてはだめですよ。経営にとって『避けられぬ仕事』と『無駄な汗』というものがあるんです。その区別のつかない『省力』は、結果的に損をする『省略』に過ぎなくなる。そもそも雪の降らない地域で、収穫後の耕うんというのは、手間不足を悩むほど日をせく仕事なのだろうか?『耕すこと』の損得勘定はその仕事をした後で考えれば分かることのはず」
と聞かされた。
「夏に1時間分の作業をしないですむのであれば、仮に冬の間に数日の手間がかかったとしても得をしたと考えるのが、経営者としての見方なのではないか。農家にとって夏は戦場。そこで鉄砲の掃除をしてたのでは間に合わないのです。夏に仕事に追われるかいなかは、暇な冬の間に夏の仕事が少なくなるよう手が打ってあるかどうかで決まる。『冬に働ける者』が勝者なんですよ」
と高松さんは話す。
そして、寒の間の反転耕が、どれほど夏の草取りを減らし、深い作土が作を確かなものにして栽培を安定化させ、夏を楽にするかは、体験している人であれば分かるはずだという。「反転耕」をするというのが「耕すこと」なのであり、それはただ単に土を柔らかくすることとは違うのだ、と高松さんは強調する。みすみす夏が忙しくなるような「省略」なんて、「省力」にも「低コスト化」にもつながらないと言うのだ。
このことは僕がお話を伺えた優れた農業経営者たちに共通する考え方だった。
滋賀県の中主町で40haの稲作を二人の後継者とともに経営する中道登喜造さんからは、
「もし規模を拡大したいと思うなら、深く耕しなさい」
と聞かされた。そして二人の後継者は「冬にこそ働く」ことを実践していた。
北海道の栗山町で300haの小麦作を30年間も続ける勝部徳太郎翁もまた、
「五反分で食える者でなければ規模の拡大はできないよ」と、300haの現在を語るのでなく、その基盤を大事に考えるゆえに「飯が食える者」とそうでない者の違いを話してくれた。
これらの人びとは、規模だけでなくその経営成果を含めて新政策の水準をすでに実現している家族経営の経営者である。自らの投資によっての基盤整備を含め機械化レベルも極めて高いが、何よりも耕すことにこだわる。それが結局もっとも安くつくことをご存知だからなのだろう。
省力・低コスト化のための集約農法
「労働時間の短縮」「労働単価の向上」などという理由を付けて、単に総労働時間を減らしてみたところで、その省力の結果が「作」を危うくし、余分な「対策」を必要とさせるのであれば、その「省力」は経営に何をもたらすのかということだろう。
我われは「省力」とか「低コスト」だとかいう「はやり言葉」に少しふり回され過ぎてはいないだろうか。
もちろんそれは必要である。しかし、その省力・低コスト化のためにと語られる技術が、農業経営の原点を見失った技術観(経営観)によって道案内されていく時、我われの経営は自ら墓穴を掘る形で自滅への道に陥ることになるのだ、ということを忘れてはなるまい。
農業とは「土」という極めて効率のよい「無人工場」を有効に生かすことによって成り立っている。そこで働いているのは作物自身であり微生物たちである。人はその管理労働をしているにすぎないのだ。
しかし、時として我われは、実は自分自身がこの無人工場をまかされた管理人であることを忘れて、工場内はゴミだらけサビだらけにしたまま、手前勝手により高い生産を求めてしまっているのではないか。
その背景には、食うに困らなくなり、いかにも便利そうに見える技術手段を手にしてきた過程で逆に失っているものを省みぬ鈍感さ、あるいは偶然の幸運によってもたらされたに過ぎない現在の豊かさや生産力の持つ危うさへの無疑問さがありはしないか。
食糧自給率の問題でも、日本農業を守るという問題でもなく、小さくとも一つの経営をあずかる者の生き残るための自問として、「省力」「低コスト化」の検証と、であればこその「集約農法」を、改めて問うてみる必要はないだろうか。




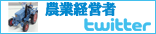



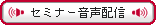



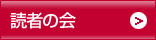

Vsxhvh - male ed pills Twcqpk