| 編集長コラム | ||
農業就業者数ではなく農業経営者数を問え | 農業経営者 6月号 | (1997/06/01)
すでに我が国の農家のほとんどは経済的には農業に依存する必要がなくなった。昔から人は農業をしたくて農家であったわけではない。農家だから農業をしてきただけなのである。社会発展の歴史あるいは産業化とは、人が農業生産の場から離れていく歴史であるとも言える。かつては農業をすること以外、生活の糧を得る方法が他にはなかったのである。我が国では、産業経済の発展にともなう農業就業人口の減少や本格的な兼業化の進行は昭和40年代に始まった。社会の生産力が上がり労働力需要が高まれば、農家が農業から離れていくのは当然の成り行きだった。女性の社会進出も同じことなのである。
多くの農家が兼業という形で農業に片足を残し続けたのは、むしろ経済的な問題以外の理由が大きかった。世間の目を気にしてのことであり、また農業が面白いからでもあった。
多くの兼業農家たちにとっては、彼らが伝統的な意味では農家である必要がなくなったからこそ、「農家であること」の豊かさに自信を持ち、それを楽しむ時代になったとすら言えるのだ。
すでに彼らにとって農業とは、経済的な必要から行なわれる「仕事」ではなく、「農家であること」の豊かさを楽しむ「趣味」になっているといったら言い過ぎだろうか。かかる経費や手間を考えたら本当は米作りなんて止めたいのだけど、隣近所の手前もあって止められないという場合も少なくないだろう。しかし、それも数年の内には米への依存度の高い純農村部においてすら変わっていくだろう。いくら趣味とはいえ、かつての機械化兼業の時代とは異なり経営者能力の無い人でも農業経営のできる時代は終わろうとしているからだ。そして、地主や請負に出すことへの世間の目も気にならなくなり始めているからである。すでに日本の農家は、飢えと隣り合わせにある自給自足時代の農業や農村の論理に縛られる必要がなくなったのだ。
そして、「生活人」としての農家が農業をする時代から、「職業人」として自覚的に農業を選び、農業を経営として発展させようとする「農業経営者」が担う産業としての農業の時代が始まろうとしているのである。今後も高齢者や兼業農家の人々が果す役割も小さなものではないだろう。しかし、それはあくまで補完的なものなのであり、その前提にあるのは「農業経営者」たちの存在なのである。職業人としての「農業経営者」と生活人としての「農家」とは同じ顔付きをしていても全く別な存在なのである。
いわゆる「農業問題」を論じる多くの農業関係者たちは、農業経営者と農家の存在を同じレベルで語ろうとし、相変わらず農業を共同体の問題、地方自治の問題、あるいは多くは役割を終えた農協の組織改革の問題にすり替えようとしている。共同体や自治の問題と産業あるいは事業としての「農業経営」の問題とは、切り離して考えるべきなのだ。そして、事業としての農業、農業経営者の問題を中心に据えて農業を語らない限り、実は、彼らが問う「農業問題」も答えが出てこないのである。
農業経営者たちもまた、農業や農村についての運命共同体的調和を前提とした農業観や経営観から自由になり、まず何よりも一人の経営者としての主体確立や経営者自身の「経営のありよう」こそを問うべきである。行政や農協が、あるいは農業関係者たちが居場所作りのため語る「農業問題」に取り込まれることによって、己れの経営問題や経営者能力の問題を曖昧にすべきではないのだ。
そのことは農業経営者が共同体や他の農家の存在に無頓着であるということではない。むしろ一人の事業者として顧客や社会に対する責任を全うすることによって、共同体や他の農家への責務を果していくべきなのだ。顧客としての農家にサービスを提供し、雇用の場を与えるといった新しい時代の農業経営者の役割と責務が背負わされていると言うべきなのだ。
「農業経営者」とは経営規模や売上の多少の区別で語られるものではない。己れを一個の自立した事業者として自覚し、農業経営者として経営を継続、発展させる意志を持つ人々のことである。
よく、農業就業人口の減少や新規学卒者の農業就業の少なさを嘆く議論があるが、それはナンセンスである。農業労働者としての「農業就業者の数」ではなく「農業経営者の数」こそが問題なのだ。そして、本誌連載執筆者の新海和夫氏のようなサラリーマン生活の後に農業経営を受け継ごうという人、世襲する農家の跡継ぎたちばかりでなく、農業をしたいと希望を持つ非農家の子供たちも沢山いるのである。




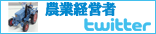



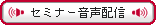



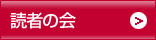

how to use tinder , how to use tinder
tinder date