| 編集長コラム | ||
時代の変化は最終コーナーに | 農業経営者 1月号 | (2003/01/01)
印象的だったのは、減反の配分やその管理という農業利権がかかわっているのにもかかわらず、自民党農林部によるさしたる抵抗も無いまま、与党・自民党が「米政策改革大綱」を通したことである。
しかし、農業界が考えるほど世間はその変化に注目を向けてはいない。なぜなら、それは、あまりにあたりまえだからだ。
農水省が「『食』と『農』の再生プラン」において、わざわざ「消費者に軸足を移した農林水産行政を進めます」などというあたりまえのことを宣言したのも、これまでの農林行政が時代の変化を無視して農業界や農業関連業界に軸足を置いて行われてきたことへの反省であり、敢えてそれを宣言せざるを得ないほど、国民の批判が大きくなったからである。
もとより農業は“食べる者”のためにある。生産者だ消費者だと言う前に、共に“お天道様の消費者”だからだ。それを、「生産」と「消費」とに別け、分断して管理することで自らの位置を守ってきた農林水産行政の論理が破綻したと言うべきなのである。
まさに、今月号のルポの主人公である矢久保英吾氏が語る“米の呪縛”に囚われた農業の世界だけが浦島太郎になっていただけなのだ。
「再生プラン」が、食品流通における信用恐慌とでも言うべき不安を招来させているBSE問題に端を発したのは象徴的であった。それをきっかけにして、メディアは様々な虚偽表示にかかわる事件を告発しはじめた。中国産野菜の農薬残留問題も、当初はそれで漁夫の利を期待した我が国の農業界であったが、無登録農薬事件が明るみに出るにいたって、“国産農産物は安心”という“幻想”も壊れてきている。それを放置してきた政治と行政の責任は言うまでも無いが、保護と利権とお目こぼしの上で、自ら事業経営者としての責任を問うことをしてこなかった農家の在り様や関連業界の自己改革能力が問われているのである。
問われている “農業問題”とは、農家や農業界がどう生き残るかではなく、我々が食べる者のために必要とされる存在であるか否かということなのだ。でなければ、我々の誇りある未来は無い。また、“農業の持つ環境保全機能”だとか“地産地消”等と言う議論を農業界が自らの存在理由として語るのも、農業を続けようと思えばこそ、あたりまえのことなのであり、消費者に恩を着せて声高に言うことでもないだろうと、僕は思う。こんなヌクヌクとした農業界が前提として、そんなお題目が貿易交渉の議論として諸外国は納得してくれるものなのだろうか。むしろ、これまでの我が農業界は、どれだけその努力をしてきたのかを自ら問うべきだ。
農業人がもうそろそろ“士農工商”の論理から開放されること。自らの責任で時代に必要とされる存在になるために我々一人ひとりが自らを問い直すことの中からしか望むべく未来は生まれない。人それぞれの農業であればよいであり、日本のいう豊かな社会の中であれば、農業には多様な可能性があるはずだ。また、今年も同じことを書いていく。




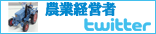



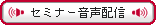



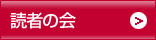

tinder online , tinder app
tindr