| 時流 | 貸しはがし事件記 | ||
集落営農の犠牲者
岩手県北上市で起こっている「貸しはがし」事件記
最終回 | 農業経営者7月号 | (2007/07/01)
(秋山基+本誌特別取材班)
地権者による助成金の奪還
本誌がこの問題を最初に農水省に伝えたのは、昨年の10月中旬だった。その席で、同省経営政策課の担当者らは「集落営農組織側の意図がどうもよくわからない」と首をひねった。
北藤根の組織は、水稲の面積だけで、すでに20ha以上という集落営農の要件をクリアしていた。にもかかわらず、伊藤氏に委託してきた転作部分をわざわざはがす理由が見えにくかったためだ。
「なぜ組織は無理に大豆に手を出そうとするのか。大豆を作って赤字が出れば、加入者全員で負担しなければならないのに……」と、担当者はいかにも腑に落ちないといった様子だった。
筆者も初めは同じ疑問を抱いた。転作用の機械を保有せず、技術力も未知数の集団が、なぜ自前での転作に固執するのかがよくわからなかった。
品目横断的経営安定対策に加入するための組織化なら、水田の面積で十分と考えるのが「合理的」発想だろう。転作を伊藤氏に委託し続ければ、危険な投資をせずに済む。収益性をより高めたいのであれば、水田の一部で野菜や花を栽培するという選択肢もある。
しかし、この組織はもともと、農水省の想定や制度の趣旨に沿って経営計画を立てようとはしていなかった。思惑は別な所にあったのだ。
岩手県の担い手対策担当者は、早い段階からそこに気づいていた。
「組織は産地づくり交付金の担い手加算を欲しがっている。コメだけだと利益が出ないが、交付金があれば、経営していけるという考えのようだ」と語るなど、問題の根は、転作の見返りとしての助成金制度にあると見抜いていた。
その狙いは、4月号で詳報した事業収支計画書でも明らかとなった。組織はコメを25ha、大豆を最大で10ha作付け、08年以降は毎年500万円以上の助成金を手に入れる。
つまり北藤根で起きた問題は、「集落営農の組織化に伴う貸しはがし」というよりも、集落営農の組織化を利用した「助成金の奪還」と呼ぶ方がふさわしい。組田の問題を見てもわかるように、この組織は、農地を助成金獲得の手段と見なしている節がある。
そんな組織側の姿勢に気づいた農水省関係者はこう語る。
「彼らはかなりビジネスライクだということ。それまで実耕作者に回っていた蕫天から降ってくる金﨟の取り分をなんとか増やそうと考えたのだろう」
その意味では、組織のリーダーたちは、冒頭の官僚たちや筆者の思考を上回って、「合理的」と言えるのかもしれない。倫理感や長期的な見通しには疑問符をつけたくなるが、目の前に「降ってくる金」はしっかりつかもうとしている。
よどんだ構造の表面化
ただし、組織側にも見誤りがあった。転作用の機械と技術を持つ伊藤氏を抱き込めなかったことだ。
当初、組織の代表者は「(伊藤氏が)組織に入ってくれるように説得する。彼がいれば、機械投資をしなくて済むし、オペレーターになってもらってもいい」と自信たっぷりだった。
組織の有力メンバーでもある北上市農協組合長も「彼(伊藤氏)自身も素直になって、集落に貢献することを考えた方がいい」と議論の方向をねじ曲げて、伊藤氏への締め付けをかけ続けた。
それでも伊藤氏が頑として加入を拒むと、貸しはがしは強行された。
「組織側は『なにくそ!』と感情的になった。伊藤氏を誘うなら、2~3年じっくり時間をかけ、先進事例を見るなどしてからでもよかったのに、入り口で間違えた」(県の担い手対策担当者)
対立の原因を考える上では、専業農家と兼業農家の意識の違いも見落としてはならない。
いみじくも組織の代表者は「うちの地区では、農家といってもみんなサラリーマン。伊藤栄喜は特別なんだ」と話した。だから地域農業を持続させるのは大変だと言いたげな口ぶりだったが、それは自らを偽った認識だ。
建設業を営んできた代表者も、市職員や農協職員として暮らしてきた組織側幹部たちも、内心ではすでに「自分は農家ではない」と気づいているはずだ。それなのに、自分たちが、真の担い手の経営を圧迫している矛盾からは、意図的に目を背けている。
同じことを、ある農政関係者は「生活に困る人と困らない人の対立」と表現した。農業を続けなければ生活に困る専業農家が、農業をしなくても生活に困らない兼業農家によって、経営を圧迫される状況を指している。
「多数決によって後者が前者をいじめるのが蕫むらの論理﨟。不条理に見えるが、これは日本型土地利用型農業の蕫土着性﨟としか言いようがない」と、あきらめ気味にこの関係者は語った。
見方を変えれば、組織側の地権者たちは農地という呪縛にとらわれている。しかし、農業改革は、集落営農を施策の対象に取り込んだことで、呪縛を解くのではなく、強める方に働いてしまった。
その結果、地権者が農地の所有権を盾に、専業農家の経営を縛りつけ、地域農業を停滞させかねない危険性が一層増した。貸しはがしは、形骸化しつつある農業集落の底辺にたまった「よどみ」の表面化にほかならない。
「間に合わせ」に終始した行政
貸しはがしを政策によって誘発しておきながら、農水省は小手先の責任回避や弥縫策を繰り返してきた。
その一端は、たとえば11月27日付経営政策課長名の通知にも垣間見られる。筆者は新年合併号で「内容は踏み込んでいる」と書いたが、この通知が、朝日新聞がこの問題を報じた当日に出されている点にも、着目すべきだろう。
実は、翌28日の衆院農林水産委員会で、民主党代議士が朝日の記事を基に、貸しはがしへの農水省の対処について質問している。これに対し、政府参考人(経営局長)はこう答弁した。
「昨日、市町村、農業委員会等の関係指導機関に対しまして、各地での農地の利用調整状況の的確な把握とともに、問題がある地区の指導に際しては、必要に応じまして、地方農政局、農政事務所等の国の出先機関に対してこれら指導機関が相談をするよう、改めて指導させていただいております」(衆院議事録から抜粋)
これでは「国会対応」で通知を出したと認めているようなものだ。
付け加えると、この通知は、現場に近い行政関係者の間で、かなり評判が悪かった。
「国はやるだけのことはやったと言いたいのだろう」「あれを北藤根に持っていって解決するなら楽な話」「実態を報告したら、国は責任をもってどちらかに軍配を上げられるのか」など、反発の声がすぐに上がった。
貸しはがしの相談窓口設置に向けての動きも、遅さとぎこちなさが目についた。
本欄では、「緊急リポート」の形で始まった昨年11月号で、本間正義東京大学大学院教授の「相談窓口を緊急に作るべきだ」とのコメントを載せた。
編集長名で農水省に出した質問状の中でも、「地方農政局等に相談窓口を設け、相談を受け付ける考えはあるか」と尋ねた。けれども同省は窓口を作る構えを一向に見せず、11月17日付の回答書では、この質問項目自体を黙殺した。
ところが明けて1月16日、事態を重く見た北陸農政局が、独自に貸しはがしの相談窓口を設置した。これを知り、最も頭を悩ませたのは本省の経営政策課だった。ずっと「地域で解決すべき」と言い続けてきたのに、国が関与する形ができてしまったためだ。しかも北陸に窓口ができたからには、全国で同じ対応をしないと整合性が損なわれる。
そこで本省では、10日遅れの同月26日に、まず霞が関の経営政策課に窓口を設けて、つじつまを合わせた。これを受け、29日から31日にかけて、東北・関東・東海・近畿・中国四国・九州の各地方農政局で相談体制が整えられた。
しかし、この慌ただしさに、読者は疑問を感じないだろうか。
NHKが「地域発!どうする日本」で、貸しはがし問題を取り上げたのは2月2日だ。1月末時点で、番組に松岡利勝農相が生出演することも決まっていた。
伊藤氏が東北農政局に電話で相談したのは1月30日。そして番組前日の2月1日、同農政局から伊藤氏に「県と市農業委員会が間に入って、組織側との話し合いの場を設ける」と連絡があった。
対処した点は評価できるにせよ、やはり番組に備えた「間に合わせ」の感は否めない。
一連の動きを見ると、行政諸機関の対応は臨機応変とも言いがたい。個人的に伊藤氏への「同情」を口にする人たちはいても、常に官の都合が優先された。
もっと早く行政が歩調を合わせて事に当たっていれば、あるいは組織が設立の準備をしていた段階で、より適切な助言がなされていれば、問題はここまでこじれなかったのではないかと、筆者には思えてならない。
先月号で書いた組田の問題にも触れておく。北上市農政課は、4月も半ばをすぎて、組織側に話し合いの場を作るよう提案した。しかし、代表者に「その必要はない」と一蹴されると、説得をあきらめた。今度こそ、農政事務所や県と連携するかと思いきや、その気配もない。市担当者の間では、手詰まりの雰囲気だけが漂い始めている。
自ら矛盾を背負い不合理を克服する
昨年10月以来、筆者はこの問題を取材してきて、日本の農業経営者が置かれている環境の厳しさを思い知らされた。
貸しはがし問題が浮き彫りにしたのは、農業経営者の経営基盤がいかに脆弱かという事実だった。伊藤氏ばかりでなく、借地や作業受託で規模を拡大してきた本誌読者の多くが、ある日突然、過去の努力を全否定され、生産資源を奪われる危険にさらされている。それが日本農業のまぎれもない現実だ。
行政がいかに当てにならないかということも、つくづく感じた。本誌が掲げてきた「国を頼るな」というキーワードは、今後も農業経営者の心得であり続けるに違いない。
あえて一介のライターの分を越えて言うならば、不合理を乗り越えられるのは経営者しかいない。
経営者とは、世の中のあらゆる矛盾をその背中で引き受け、自己革新を通じて事業を前進させることで、現実を変えていく存在だと筆者は考える。
農業界に真の経営者が育っていく過程で、この歪んだ世界にようやく理性の光が当たり、不合理が克服される。時代を変えるのは政治家でも官僚でもない。現実を背負った一人ひとりの経営者たちだ。
伊藤氏が今年失う面積は約6haと確定した。来年はさらに約1haが集落営農によってはがされる。
「収量増を目指すと自信を持っては言えないけれど、当面はコスト減で対応していく。経費削減の算段はとった」と伊藤氏は話す。
今年から試作するジャガイモは植え付けが終わり、5月中旬には田植えが始まった。大豆を播種する時期も近づいてきた。
伊藤氏は今、前を向いている。




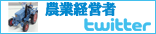



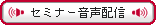



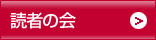

cheapest viagra