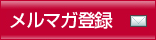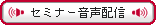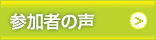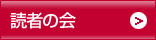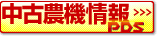HOME >2007年11月
| 特集 | ||
ヒット商品のつくり方
時代に求められる農場発の商品開発 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)

消費者のライフスタイルと密接な関係にある食の世界では、顧客ニーズは常に変化し続ける。そのなかで登場するヒット商品は、どのような背景のもとで生まれるのだろうか。今回の特集では、注目のアイテムを紹介しながら、商品開発のヒントを探る。
消費者ニーズから逆算し「ほかにないもの」を創造する
作れば売れた時代から、売れなければ作れない時代へ――。(有)米シスト庄内の代表取締役社長、佐藤彰一氏は、変貌する農業界について、決して揶揄することなく、自戒の念をこめてそう話す。
自らの生産物の価値をいかにして高め、消費者に求められる「商品」へと昇華させるのか。
数々のオリジナル商品を世に放っている同氏に、商品開発にかける想いを聞いた。
(以下つづく)
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
第41回 息子が受け継いだのは
困難に挑戦した親の誇り | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
【(有)ピーストータルアドバイザー 家子憲昭
代表取締役 家子秀都(岩手県奥州市江刺区)】
代表取締役 家子秀都(岩手県奥州市江刺区)】

 かつて家子憲昭が食管法の中に生きる農民の怒りから始めた
かつて家子憲昭が食管法の中に生きる農民の怒りから始めた「ライズみちのく」の事業は、憲昭の事業としては破たんした。
憲昭の生きた農業経営者の誇りをかけた挑戦とは何であったのだろうか。
しかし、少なくとも家子憲昭はその生き様において、
長男秀都に人が次代に受け継がせるべき最も価値ある「誇り」を伝えた。
憲昭の父を含めて、家子家三代に受け継がれたものとは何か?(以下つづく)
| 農業経営者取材 | スーパー読者の経営力が選ぶ あの商品この技術 | ||
北海道上川郡美瑛町 尾形恭男氏が選んだ商品 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
 風光明媚な観光地として知られるアップダウンの激しい畑作地帯は、その地の農業経営者に過酷かつ危険な作業条件を強いている。
風光明媚な観光地として知られるアップダウンの激しい畑作地帯は、その地の農業経営者に過酷かつ危険な作業条件を強いている。メーカーの独自仕様機はもちろん、現場の創意工夫で生まれた様々な技術が、悪条件下の作業を効率化し、ダイナミックな輪作栽培を支えている。
【経営データ】
■ 面積/畑作26ha。春播き小麦1ha、秋播き小麦9ha、ビート5.2ha、ジャガイモ6ha、大豆1.8ha、小豆1.5ha、カボチャ1.5haを輪作。ジャガイモはカルビーポテトとの契約栽培のスノーデン2ha、イオンのブランド「トップバリュグリーンアイ」用のトヨシロ1ha、農協・首都圏の生協個配・名古屋の老舗スーパー向けの男爵3ha。
■労務構成/夫婦と両親の4名+非常勤の親類。
■労務構成/夫婦と両親の4名+非常勤の親類。
| 提言 | 視点 | ||
こだわりから共有の農業経営 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
| 農業技術 | 乾田直播による水田経営革新 | ||
Vol.21 北海道の直播栽培 その2 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
【コメ産業コンサルタント 田牧一郎 -profile
】
石狩平野の中心に位置する美唄市は、水田面積5400ha、06年の水稲作付面積は2600haと、北海道内でも有数の穀倉地帯である。札幌からの車窓には水稲、大豆、トウモロコシ畑と、耕地が広がっていた。
北海道農業研究センターの大下泰生氏のご案内をいただき、直播栽培に長年取り組んできJA美唄を訪問した。組合長の林晃氏からJA管内農業の概要説明を受け、営農技術主幹の粟崎弘利氏から、直播栽培への具体的な取り組みについてうかがった。粟崎氏は長年にわたり北海道農業研究センターで乾田直播技術の開発に携わっており、現在はJA美唄で乾田播種早期湛水栽培の普及も含めた生産技術指導をされている。
| 農業技術 | 防除LABO | ||
第27回 ブドウ編
雨除け栽培と有機志向の土壌管理で
晩腐病やべと病を撃退の巻 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
厄介なべと病は、初期のうちに切り札の薬剤で確実に叩く
専門家 常陸太田市はブドウが盛んな地域のようですね。「常陸青龍(ひたちせいりゅう)」が次世代の高級品種として人気上昇していると聞いています。
武藤 阿武隈山地の南端にあたるこのあたりは、ブドウやナシなどの果樹栽培農家が多いですね。後継者も育っています。うちの部会では45年前からブドウを作っていますが、私が今44歳なので、ブドウと共に人生を歩んでいるようなものですね。
専門家 それはいいことですね。活力ある産地からブランドは生まれてくるものですから期待できます。では、さっそく防除の話に移りましょう。
武藤 一番困ったのは晩腐病。以前30aほどの「伊豆錦」を晩腐病で売上ゼロにしてしまい、ショックを受けました。県の先生方と2年くらい勉強して、5年前から雨除け栽培を導入したんです。設置した次の年は、発病がパタリと止みました。(以下つつづく)
| 時流 | 農・業界【国内】 | ||
カズサ愛彩ガーデンファーム(千葉県君津市)
首都圏からのシニア層や家族連れで賑わう
アグリアドバンスのスタッフが栽培指導 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
| 時流 | 農・業界【国内】 | ||
農業体験農園「百匁の里」(東京都練馬区)
ベジフルサミット・枝豆部門で入賞
都市野菜の美味しさ伝わる | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
| 時流 | 農・業界【国内】 | ||
「ふくしま食の商談会」開催(福島県郡山市)
生産者・加工業者145社が出展
恒例の個別商談も好評 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
| 時流 | 農・業界【国内】 | ||
全国農業青年クラブ連絡協議会ほか
全国農業青年交換大会開催
次世代を担う農業青年が多数参加 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
| 時流 | 土門「辛」聞 | ||
もはや予算も対策もなし。
あるのは米政策改革大綱のみ | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
【土門 剛 -profile
】
米価低落の「対策」?アンケート調査の無意味さ
農水省食糧部計画課が、日本農業法人協会を通じて「18年産米に係る実態調査」と題したアンケート調査を実施したのは、絆創膏大臣で大騒動していた真夏のことだった。笑ってしまうのは、日本農業法人協会が会員にアンケート用紙を送った際に添付した依頼文書の頓珍漢ぶりである。
「米販売価格の低落は、農業経営に深刻な影響を与えております。与党自由民主党における先の参議院選挙の総括論議の中で、特に農村票の減少については、米価の低落を挙げる声も多く、それに対する対策を政府に求める声も高まっております。品目横断的経営安定対策の成否も米価が及ぼす影響が無視できない等の見方も漸く政府内に生じております」
米価低落の対策って、何があるのだろうか。頭を冷やしてよ~く考えてみるべきだ。米政策改革大綱には、そんなことは一行も書いていない。あるとすれば減反ぐらいだ。それも売れない者が減反に協力し、売れる者にコメを目一杯作ってもらいたいと書いてある。 (以下つづく)
| GAP | ||
GAPレポート第5回 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
「中国食品は危ない」との報道が過熱するなか、
中国農場の実力を見誤るな
日本の先を行く中国GAP事情を直視せよ!

中国ではEUへの果実の輸出増加などを背景に、GAPが急速に普及している。現在約300の農場がGAP認証を取得し、GAPの研修を受けた人が5万人におよぶ。日本では「中国製の食品は危ない」という報道が過熱しているが、中国産農産物の世界における位置づけが高まっている現実にも目を向ける必要がある。
このところ、中国製の食品に対するバッシング、ネガティブキャンペーンが繰り広げられている。練り歯磨きに始まり、ドッグフード、ウナギ、段ボール入り肉まんと「中国製は危ない」という情報がマスコミを通じて大々的に報じられており、とどまるところを知らない。
「やらせ」だった段ボール入り肉まんを除き、一部の企業、商品についてはおそらく報じられた通りだろう。しかし、他方ではきわめて安全性が高く、衛生的な食品が生産されており、世界での評価を高めていることを無視すべきではない。メイドインチャイニーズが世界のマーケットで確実に布石を打っていることはGAPへの取り組みからもわかる。
(以下つづく)
世界70カ国の約5万農場が認証を取得するまで成長したユーレップGAP。農場管理における事実上の世界スタンダードになっている。我が国では日本版GAP(JGAP)の普及が始まったばかり。本誌では、農場の経営管理手法そして国際競争に生き残るための規範として、GAPに注目。世界の動き、日本での進展を毎月報告する。レポートはジャーナリストの青山浩子氏。 -profile
| 編集長コラム | ||
本誌は「自己破産の勧め」を特集する | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
【「農業経営者」編集長 昆 吉則 -profile
】
本誌では、昨年の12月号(131号)で「農業経営から撤退する自由」を特集した。農業経営者を励ますためにある本誌が、農業からの撤退を語ることに読者から驚きの反応もあった。しかし、本誌では次号でさらに「自己破産の勧め(仮)」という特集を計画している。それが、今、危機に瀕している農業経営者に対する人生の励ましになると思うからだ。そして、先月の当欄では「死ぬな、死なすな」とも筆者は書いた。 | 農業経営者コラム | 高橋がなりのアグリの猫 | ||
高橋がなりの「アグリの猫」
第7回 すいません!今までサボッてました。 | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)
【国立ファーム有限会社代表 高橋がなり -profile
】
本誌読者のみなさま、すいません! やっと僕が本気になりました。
これまでの国立ファームは、僕が前面に出ることはしないで「すべてのシステムを自分たちで考えなさい」というスタンスで、決して前に出ないように心がけていました。それは、たくさんの失敗の中から、多くのことを社員たちに学んでほしいと願っていたからでした。
けれども、もうそんな悠長なことは言っていられません。「死ぬか、生きるか」という状況の中では、僕は迷わず「生きること」を選びます。そこまで僕は追いつめられています。
8月から僕は、生産部、商品部、飲食部、そして青果販売部の四部門の部長職を兼任し、自ら陣頭指揮を執って会社の改善に乗り出すことにしました。今、僕の頭の中では生産部長の僕と商品部長の僕が、「ここはお前が譲れ」とか「ここはお前に任せた」などと、活発な議論がなされているところです。(以下つづく)
| トラクタ | ||
ナフィールドトラクタ | 農業経営者 11月号 | (2007/11/01)

型式・仕様:342型・42馬力
製造社・国:ナフィールド社・英国
製造年度:1962(昭和37)年
使用過程:この機種は1962年ころから(株)新宮商工が輸入販売を始めた。北海道音威子府村の三次和巳氏が入手し(それ以前の経過は不明)、1989年6月に北海道札幌市の伊藤二郎氏が譲り受け所蔵していた。
| *編集長ブログ | ||
NHK一連の農業番組「ライスショック」「日本の、これから『どうする?私たちの主食』」を見る (2007/11/01)
このブログは下記アドレスに移動しました
http://blog.goo.ne.jp/kon_nou2007/
僕もブログというものを始めることになった。始めると言うより、スタッフの強要によって始めさせられるのである。
しかし、ほぼ同世代の大泉一貫氏(http://www.ohizumi.jp/)や市川稔氏(http://irb.co.jp/)の勤勉さを知っているだけに、怠け者の僕もやって みるかという気になった。
それに、このところ、NHKをはじめ各メディアがやたらと農業を取り上げるようになった。僕のところにも、企画の相談や取材でたくさんのジャーナリ ストが来る。NHK、TV朝日、週刊ダイアモンド、週刊エコノミスト、VOICE等々。
民主党のいんちき政策と参議院選敗北後の自民党のうろたえ、そしてついに 破たんした農協のコメ流通支配に、一般メディアもあらためて農業ネタが売れると読んだのだろう。
- ライスショック(大きな国で)
- 何がどうおいしいを数字ではっきりと(花総果菜)
- 農業起業講座。(ほぼ日刊三浦タカヒロ。)
- 広島で屋上緑化かるいちばんとカルベラの展示です♪♪♪(Urban Green Life 街にもっと緑を・・・ 兼定興産の屋上緑化土「かるいちばん」)




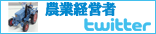

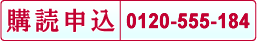
 消費者ベースではほとんどの野菜は色や形といった「見た目」で評価されるケースが多いが、外見ではなく「中身を正しく評価しよう」というのが、当社の考えだ。それを実証し、定着させるために野菜の成分分析業務も行なっている。納品された野菜野菜のビタミンC、糖度、硝酸などの含有量や野菜の力(抗酸化力、免疫力、解毒力)を分析する。はじき出された数値を生産者にフィードバックし、より栄養価が高く、「旬」に近い野菜を作るものである。
消費者ベースではほとんどの野菜は色や形といった「見た目」で評価されるケースが多いが、外見ではなく「中身を正しく評価しよう」というのが、当社の考えだ。それを実証し、定着させるために野菜の成分分析業務も行なっている。納品された野菜野菜のビタミンC、糖度、硝酸などの含有量や野菜の力(抗酸化力、免疫力、解毒力)を分析する。はじき出された数値を生産者にフィードバックし、より栄養価が高く、「旬」に近い野菜を作るものである。