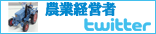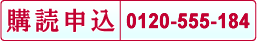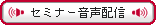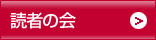農業経営者取材 [75]
- 新・農業経営者ルポ [47]
- スーパー読者の経営力が選ぶ あの商品この技術 [28]
- 叶芳和が尋ねる「新世代の挑戦」 [13]
農業経営者コラム [51]
- 激突対談・高橋がなり×木内博一 [1]
- 高橋がなりのアグリの猫 [26]
- ヒール宮井の憎まれ口通信 [14]
- 木内博一の和のマネジメントと郷の精神 [7]
- 幸せを見える化する農業ビジネス [5]
提言 [60]
- 視点 [60]
農業技術 [68]
- 大規模輪作営農のための乾田直播技術 [6]
- “Made by Japanese”による南米でのコメ作り [6]
- 乾田直播による水田経営革新 [23]
- 防除LABO [31]
農業機械 [23]
- 土を考える会 [1]
- 機械屋トラクタ目利き塾 [16]
- 機械屋メンテ塾 [6]
- 機械屋インプルメント目利き塾 [2]
農業商品 [8]
- 読者の資料請求ランキング [8]
時流 [287]
海外情報 [3]
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
私が売るのは、イチゴではありません | 農業経営者 3月号 | (2009/03/01)
【(有)ストロベリーフィールズ 遠藤健二(茨城県下妻市)】
 「新規就農」から10年目の遠藤健二は、最高品質のイチゴを栽培する生産技術者である。しかし、遠藤は「生産者」と呼ばれることを嫌う。彼はイチゴではなく遠藤オリジナルの「商品」を作っているからだ。加工品ではなく、イチゴそのものでいかに「商品」を企画するか。そこに遠藤の農業経営者としてのセンスが示されている。
「新規就農」から10年目の遠藤健二は、最高品質のイチゴを栽培する生産技術者である。しかし、遠藤は「生産者」と呼ばれることを嫌う。彼はイチゴではなく遠藤オリジナルの「商品」を作っているからだ。加工品ではなく、イチゴそのものでいかに「商品」を企画するか。そこに遠藤の農業経営者としてのセンスが示されている。非農家出身の新規就農者が最高レベルのイチゴ生産者に
本誌2月号の裏表紙、国立ファームの広告「農業改革・国立ファームNEWS」を覚えておいでだろうか。紅白のイチゴの写真とともに、同社が12月から新宿の高級デパートでホワイトイチゴを販売開始した旨の紹介がなされている。小売の初値は紅白18粒入りで8400円とある。国立ファームに問い合わせてみると、その後も連日完売の人気商品になっているという。このホワイトイチゴの生産を担当しているのが、今回紹介する遠藤健二である。
遠藤は、楽天の様々なイチゴ販売部門で売れ筋ランキング第一位の座を維持している人物でもある。非農家の出身で、いわゆる「新規就農者」だ。そんな遠藤が、「就農」から約10年目にして最高レベルのイチゴ生産者になり、商品開発やマーケティングにおいてもリードしているのである。
バブルに背を向け、生き方を模索した学生時代
遠藤は、本誌執筆者の一人である宮城大学大学院の大泉一貫教授とも因縁がある。仙台で農業とはまったく関係ないサラリーマンの家庭で育ち、1986年に東北大学農学部に入学。3年生で同大学の助教授だった大泉のゼミに入る。それが農業に関わるきっかけだった。卒業後は就職もせず、「大泉先生のかばん持ち」をしていたと遠藤は笑う。
大学の卒業年次は90年。まさにバブル真只中の好景気が遠藤の学生時代と重なっていた。望めば就職は公務員でも民間企業でも選り取りみどりだっただろう。
しかし、そんな世間の気分に馴染めなかった。浮かれ立つ世のなかで自らの居所を見いだせず、これからの人生に対しても目標を持てずにいた。進むべき道を模索しようと、休みには米国や中国などをバックパッカーとして歩き回った。海外で出会う同世代の若者たちの確固たる目標や、人生に対する意思を見聞きするにつけ、自分自身や日本人のひ弱さを痛感させられた。なかでも、北京で出会った中国人学生の言葉には大きな衝撃を受けた。
中国の学生は、エリートであっても(あるいはそうであればこそ)将来の勤め先は国家によって指定されてしまうと話していた。そんな中国の学生と「何のために学ぶのか? そして自分はこれから何をすべきなのか」という問いについて議論になった時のことである。遠藤が指摘した中国の国家や社会の問題を認めつつ、中国の学生は毅然としてこう言ったのだ。
「そんな国だからこそ国を変えるために自分は学び、そして国を変えていく」
以来、遠藤の耳の奥にはその中国人学生の言葉が残っていた。そして、中国を旅してから2カ月経った89年6月、北京で天安門事件が起きた。その様子は全世界に映像として流された。天安門広場で一人両手を広げて戦車に立ち向かう若者の姿は、世界の多くの人々に衝撃を与えたはずだ。遠藤が中国人学生と出会い、議論した場所は、今まさにテレビに映し出されている天安門広場。戦車の前に立つ青年があの時の学生とダブって見えた。目標も目的もなく、成り行きに任せて就職するという人生の選択肢は、もう遠藤にとってあり得なかった。
(以下つづく)
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
受け継がせたいのは、誇りごと。 | 農業経営者 2月号 | (2009/02/01)
【西山農園 西山直司(愛知県田原市)】
 農家一戸あたりの販売額が日本で最も大きい地域といわれる愛知県渥美半島で、
敢えて省力化の進んだ葉菜類を選ばず、生食用ダイコンの生産に力を入れる西山直司。>
高校時代から実学としての農業に触れ、大学卒業後に父から経営を継承すると、
工夫に満ちた工程管理や商品開発によって、季節性のあるダイコン経営を安定化させていった。
農家一戸あたりの販売額が日本で最も大きい地域といわれる愛知県渥美半島で、
敢えて省力化の進んだ葉菜類を選ばず、生食用ダイコンの生産に力を入れる西山直司。>
高校時代から実学としての農業に触れ、大学卒業後に父から経営を継承すると、
工夫に満ちた工程管理や商品開発によって、季節性のあるダイコン経営を安定化させていった。かつて松も育たたなかった原野を開拓した入植初代の祖父と、二代目の父から受け継いだのは、 優れた経営感覚だけでなく、開拓者としての誇りとチャレンジ精神だった。
先代を超えてこそ真の後継者となる 「売家と唐様で書く三代目」 と江戸川柳はいう。
書を学ぶ暇もなくひたすらに働いた初代。それを受け継ぎ家業を発展させた二代目。財を成した二代目の庇護の下で教養を積み、粋人として育った三代目。その三代目が、祖父や父が書くこともできなかった洒落た唐様の文字で「売家」と張り紙をする。 いかにもありそうな話である。
それは家業の継承だけでなく、戦後の困難のなかで豊かな国を作り上げた世代の三代目ともいえる現代日本人、あるいは新開地に入植した農家の後継者が、入植世代の開拓精神を忘れ、未来を危うくさせる姿にも重なる。
欠乏の時代ならば、貧しさは志を持った人々を強くする。しかし、労せずして与えられた豊かさのなかでは、伸びる力を持った者までもが安楽さに溺れ、夢見る力さえ萎えさせてしまう。
戻し続け、作り続けてきた土。まさにそんな「土」に象徴される、先人が未来に託した遺産の恩恵を享受するだけなら、それは怠惰な資産管理人に過ぎず、後継者と呼ぶに値しないのだ。受け継いだ誇りや理念を守りながらも、先代を超えて新しい時代と経営を創りだす者だけが、真の後継者と呼ばれるべきではないだろうか。
今回の主人公は、農家一戸あたりの販売額が日本で最も大きい地域といわれる愛知県渥美半島で、ダイコン作りに取り組む西山直司(46歳)である。
ハウス園芸による野菜や花卉、露地野菜や畜産。今でこそ渥美半島は豊かな農業地域である。 しかし、コメ作りに適さない洪積台地の農業は、70年代に入るまで貧しさのなかにあった。1968年に豊川用水が通るまでは、天水頼みの農業だったのである。昭和初期に始まった、水もなく松も育たない痩せ地への入植。食糧難だった戦後の一時期を除けば、ずっと苦労の連続だった。
田原市六連町一本木(弥栄集落)に入植した祖父・故西山忠雄は、開拓者たちのリーダーとして、早くから農協組合長などの村役に就いていた。その忠雄に代わり、西山家の農業経営を発展させたのは、渥美農高を卒業した当時から経営を任されていた二代目の父・西山作(72歳)である。
さらに作から家業を受け継いだ三代目・西山直司を通して、農業経営と開拓者精神の継承について考えてみたい。
(以下つづく)
| 新・農業経営者ルポ | ||
家族でできるからこその農業 | 農業経営者 1月号 | (2009/01/01)
【(有)いちごやさん 佐野光司(静岡県富士宮市)】
 静岡県の富士宮市で(有)いちごやさんを経営する佐野光司。
静岡県の富士宮市で(有)いちごやさんを経営する佐野光司。地元にある4店舗の大規模量販店に「いちごやさんのイチゴ」という ポップ入りの販売コーナーを与えられ、そこに日配で朝取りイチゴを出荷する。
摘み取り園を兼ねる直売所という経営スタイルの実現は、13台のイチゴの自動販売機が始まりだった。
消費者の喜ぶ顔を見るために完熟イチゴを地元に提供
「お目にかかってお話しするのは良いけど、私なんか取り上げるに足りる存在ですか?」
少し照れ臭そうに筆者を迎えた佐野光司(59歳)の顔には、その人柄がそのまま表れていた。実直で控えめで、ひたすらにイチゴ作りに打ち込んできた佐野。自然体で農業に取り組むことで、いつの間にか農協のなかでも最大規模の生産者となり、農協のイチゴ部会会長になっていた。
しかし、そんな佐野も市内各所に置いた自動販売機での直売が伸びていき、さらに地元量販店からの誘いをきっかけにして農協出荷を止めてしまった。農協に出荷するイチゴがなくなってしまったと言ったほうが正しいほど、お客さんの支持があったのだ。
農協出荷に対する不満はあっても、現実に農協出荷を止めるという結論を出すまでには、夜も眠れなくなるほど悩んだ。
そして、現在の佐野は、静岡県の富士宮市で同市内外の量販店や生協への出荷に加え、農園併設の直売所での販売とイチゴ狩りのハウスを経営している。最大13台まで増やした自動販売機も今年からは廃止した。現在の生産ハウスは、地床ハウス52a、高設のハウス20aの計72a。イチゴの食味は地床が勝ると考える佐野は、食味の良さを重視する販売用には地床のハウスを使う。一方、摘み取りの観光果樹園は、冬の寒いなかでイチゴの香りと摘み取りの楽しさを楽しんでもらうためのもの。そのためには高設栽培にすべきだし、車椅子でも入れるようにと畝間も広く取っている。
量販店や生協へは、決済こそ市場業者を通すが、朝取りにした完熟のイチゴを佐野が直接納品する。各店舗には「(有)いちごやさんの朝取りイチゴ」であることが写真と共に示されている。
完熟にして出荷するため、棚に置ける時間は限られるし、過熟になればお客さんからのクレームも出る。しかも、スーパーの営業日に合わせて年末年始も毎日出荷せねばならない。しかし、だからこそお客さんの満足度は極めて高いのだ。
さらに、量販店の棚のポップを見たお客さんが摘み取り園に来てくれる。佐野の摘み取り農園や直売所経営にとっては願ってもないことだ。それはお客さんや量販店にとっても価値がある。店にとっては佐野のイチゴ作りだけでなく、佐野という農家やハウスのことをお客さんに知ってもらうことで商品への安心を伝えることにつながる。さらに、お客さんにとっては売り場の棚を通してイチゴの摘み取りという楽しみまで体験できるのだ。お店の棚がイチゴに関するモノとしての情報だけでなく、摘み取り体験というコトの情報までも提供しているというわけだ。
生産者と小売業者が協力することで、産地ならではの最高のイチゴをより多くのお客さんに楽しんでもらうことが実現した。佐野が地元出荷にこだわるのはハウス内で完熟させたイチゴを一刻も早くお客さんに食べてもらいたいから。そして、お客さんの喜ぶ顔を実感したいからだ。収益性もさることながら、それこそが農協まかせの出荷では受けることのなかった生産者としての感激なのである。
(以下つづく)
-
農場スタッフを人財にする[前編]
- can you get cheap nortriptyline without dr prescription(04/02)
- canada pharmaceuticals online generic(04/02)
- Davidjoype(04/02)
- AzzwPriob(04/02)
- canadian pharmacy online(04/02)
経営を発展させる雇用のあり方 | 農業経営者 1月号 | (01/01)
- ライスショック(大きな国で)
- 何がどうおいしいを数字ではっきりと(花総果菜)
- 農業起業講座。(ほぼ日刊三浦タカヒロ。)
- 広島で屋上緑化かるいちばんとカルベラの展示です♪♪♪(Urban Green Life 街にもっと緑を・・・ 兼定興産の屋上緑化土「かるいちばん」)