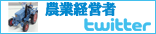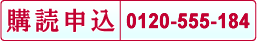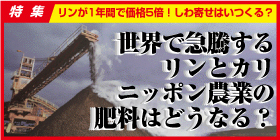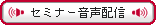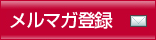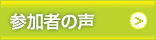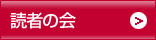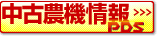HOME >2008年07月
| 特集 | ||
世界で急騰するリンとカリ
ニッポン農業の肥料はどうなる? | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
ファーミング・エンターテイメント | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
【(有)農マル園芸・(有)アグリ元気岡山 代表取締役 小川博巳(岡山県美作市)】
 大学で農業経済を学び、社会福祉団体職員を経て、父から経営移譲を受けた小川博巳。胸中には思索を積み重ねた末に導き出した一つの課題—農業のノーマライゼーション—があった。その理想が結実した岡山県内の農園には、花や野菜の直売所、イチゴの摘み取り園など、多彩な施設が備えられている。来園者が思い思いの時間を過ごす園内には、エンターテイメントに昇化した、新たな農業の姿があった。
大学で農業経済を学び、社会福祉団体職員を経て、父から経営移譲を受けた小川博巳。胸中には思索を積み重ねた末に導き出した一つの課題—農業のノーマライゼーション—があった。その理想が結実した岡山県内の農園には、花や野菜の直売所、イチゴの摘み取り園など、多彩な施設が備えられている。来園者が思い思いの時間を過ごす園内には、エンターテイメントに昇化した、新たな農業の姿があった。
良い商品、良い顧客の良循環を生む直売所作り
高い運賃と決して安くはない値段の生産者直売のコメがなぜ売れるのだろうか。産直の購入者は単に美味しいコメを求めているわけではない。農家から直接コメを買うという関係性や農家の人柄あるいはその背景にある自然や風土に触れる満足を買っているのだ。人々は空腹を満たす食糧の供給だけではなく、癒しや自然や故郷への回帰願望を満足させることを農業に求めているのだ。
埼玉県のサイボクや三重県のもくもく手作りファームなどすでに幾つかの農業アミューズメントも存在する。また観光果樹園は果樹産地の観光名所になっている。現代という「過剰の時代」であればこそ、農業には「ファーミング・エンターテイメント」というべき新しいビジネスジャンルが存在する
小川博巳(45歳)は、花を主体に野菜の直売とイチゴの摘み取り園を兼ねた農園直売所を経営する。さらにアイスクリームやスイーツのコーナーも設け、それらが相乗効果をもたらし、良質顧客の定着を実現している。そして、自らの農業ビジネスを通して農業・農村だけでなく、教育や社会福祉への貢献ができないかと小川は考えている。(以下つづく)
| 農業経営者コラム | ヒール宮井の憎まれ口通信 | ||
農地解放を再考す | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
【宮井 能雅 -profile
】

宮井家3代の歴史
香川県生まれで国鉄マンの祖父は北海道に入植し、戦前80haの地主であったが、戦後の農地解放で30haになった。昭和41年に祖父が他界した時は、私の父親は長男ではあったものの、諸般の事情で5haからのスタートだった。
| 提言 | 視点 | ||
生み出して、そして乗り越えて | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
【アキレス(株) シューズ事業部 シューズ商品企画開発部 部長 津端裕】

近年、子供靴市場は少子化の影響を受けて縮小の傾向にある。その一方で海外からの輸入品が増えて供給は過剰になり、それに伴い値段が下落している。この厳しい情勢の中、2003年に当社が発売した『瞬足』は、累計で1000万足を販売し、小学生の3人に1人が履くほどのヒット商品になった。最大の特徴は、トラックのコーナーでも地面をしっかり蹴って速く走れるように、シューズの底面が左右非対称に設計されていること。平均体力が落ちて満足に走れない子供が目立つ中で、速く走れる能力は私たちの子供の頃以上に、クラスの人気者になるための要素になっている。「足が速くなりたい!」という、昔から変わることのない欲求に応えたことで、男の子からの絶大な支持を集めた。
| 時流 | 農・業界【国内】 | ||
(株)ミツハシ(神奈川県横浜市)
GAP認証取得米を商品化
圃場から食卓まで一貫した安全体制を整備 | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
| 時流 | 農・業界【国内】 | ||
オイシックス(株)(東京都品川区)
新規ユーザー向けに音楽CD付きおためしセットを発売
妊娠中や育児中の女性を応援 | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
| 時流 | 農・業界【国内】 | ||
(株)マイファーム(大阪府高槻市)
農園レンタル事業に参入
大都市圏での展開目指す | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
| GAP | ||
GAPレポート第13回 130カ所に分散する農場でグローバルGAPを取得した(有)松本農園
「GAPの本質はリスクマネジメントにある」 | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
ニンジン、ダイコンなど露地野菜を中心に経営する(有)松本農園(熊本県益城町:松本博美代表取締役)は、2007年5月にグローバルGAPを取得。今年4月に更新した。「欧米諸国に対するチャレンジャーとしてニッポンの農場も世界標準規格をクリアすべき」と力説する松本武取締役にリスクマネジメントの本質について語ってもらった。
GAPのことは、主要取引先から時々聞いていたが、実際にどんなものか思案し続けていた。2006年春にユーレップGAP(現グローバルGAP)の事務局であるFoodplusのクリスチャン・ムーラー氏が当農場を訪れた。当社はトレーサビリティの一環として、生産時に使用した農薬・肥料などを消費者が確認できる生産情報公表JAS規格(農産物)を2005年に取得し、管理をしてきた。その内容を紹介するといたく感心し、最後に「ユーレップGAPを取得してください」と言われた。こちらもつい「任せて下さい」と言ってしまったが、それでも07年5月7日付けで認証を取得。審査の2日前に審査機関であるSGSジャパン(株)で受けた講習が非常に役に立った。GAPというとマニュアルや記録付けに目を向けがちだが、その奥にある本質がわかり、「目からうろこ」でした。
GAPが求めているものは、基本的にはHACCP(ハサップ)と同じと考えています。組織がリスクマネジメントをどこまで考えているのか、そのリスクを最小限にとどめるために何をするかということだと思います。たとえば、GAPに「救急箱を常備しているか?」といった主旨の要求項目がある。これに対し、農場の近くに病院がある経営者は、「何か起これば病院に駆け付けられるので救急箱は必要ない」と答えるかもしれない。だが、病院は24時間必ず開いているわけではない。仮に24時間開いているとしても、GAPが求めていることは「従業員の応急処置をその組織がどの範囲まで考慮しているか」だ。それを踏まえると「病院が近いから(救急箱は)要らない」という答えは適当ではない。審査員は救急箱のことを聞いているのではなく、組織がどこまでリスクを考えているかを聞いているのだから。(以下つづく)
グローバルGAP認証取得のきっかけは?
GAPのことは、主要取引先から時々聞いていたが、実際にどんなものか思案し続けていた。2006年春にユーレップGAP(現グローバルGAP)の事務局であるFoodplusのクリスチャン・ムーラー氏が当農場を訪れた。当社はトレーサビリティの一環として、生産時に使用した農薬・肥料などを消費者が確認できる生産情報公表JAS規格(農産物)を2005年に取得し、管理をしてきた。その内容を紹介するといたく感心し、最後に「ユーレップGAPを取得してください」と言われた。こちらもつい「任せて下さい」と言ってしまったが、それでも07年5月7日付けで認証を取得。審査の2日前に審査機関であるSGSジャパン(株)で受けた講習が非常に役に立った。GAPというとマニュアルや記録付けに目を向けがちだが、その奥にある本質がわかり、「目からうろこ」でした。
GAPの本質とは?
GAPが求めているものは、基本的にはHACCP(ハサップ)と同じと考えています。組織がリスクマネジメントをどこまで考えているのか、そのリスクを最小限にとどめるために何をするかということだと思います。たとえば、GAPに「救急箱を常備しているか?」といった主旨の要求項目がある。これに対し、農場の近くに病院がある経営者は、「何か起これば病院に駆け付けられるので救急箱は必要ない」と答えるかもしれない。だが、病院は24時間必ず開いているわけではない。仮に24時間開いているとしても、GAPが求めていることは「従業員の応急処置をその組織がどの範囲まで考慮しているか」だ。それを踏まえると「病院が近いから(救急箱は)要らない」という答えは適当ではない。審査員は救急箱のことを聞いているのではなく、組織がどこまでリスクを考えているかを聞いているのだから。(以下つづく)
世界70カ国の約5万農場が認証を取得するまで成長したユーレップGAP。農場管理における事実上の世界スタンダードになっている。我が国では日本版GAP(JGAP)の普及が始まったばかり。本誌では、農場の経営管理手法そして国際競争に生き残るための規範として、GAPに注目。世界の動き、日本での進展を毎月報告する。レポートはジャーナリストの青山浩子氏。 -profile
| 海外情報 | 海外レポート | ||
乾ききった大地 オーストラリアを行く
渇水の稲作現場を訪ねて | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
| 編集長コラム | ||
肥料原料問題での全農と農水省の責任 | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
【「農業経営者」編集長 昆 吉則 -profile
】
「昆さん、肥料が大変なことになってますよ。日本は完全に買い負け。ヨルダンのアラジンは原料調達ができておらず、肥料の暴騰は必至。この肥料暴騰が農家の選別に拍車をかけるでしょうね」連休明けに訪ねてきた土門剛氏が開口一番にそう言った。その話を聞いて、予定していた特集を変更し、急遽、肥料問題を今月の特集とした。
| 農業経営者コラム | 高橋がなりのアグリの猫 | ||
高橋がなりの「アグリの猫」
第15回 営業を他人まかせにしていませんか!? | 農業経営者 7月号 | (2008/07/01)
【国立ファーム有限会社代表 高橋がなり -profile
】
国立ファームが初めて生産した新顔野菜「ソルトリーフ」を飲食店へ卸すための営業部隊(今年の新卒5人組)が、毎日飛び込み営業先に叱られて帰ってきています。ありがたいことです。飛び込みで野菜を売りに来るのに野菜のことをロクに分からないワカゾウを、他人様が鍛えてくださるのですから。叱られる要因のワースト3は、3位—新顔野菜なのに基本レシピの提案や成分表示がない。2位—ソルトリーフが商品として安定していない(味・見た目にむらがある)。1位—生産量が安定していない(月によって生産量が極端に少なくなってしまう)。ご指摘いただけば当たり前のことなんですが、僕たち素人を相手にしてくれて、当たり前の事を叱っていただいていることを本当にありがたいと思っています。
もともとは飲食店への営業は考えていませんで、大卸さんや中卸さんへ営業をして簡単に売り捌いてしまう予定でした。楽をしようとすると痛い目に遭うのが世の常で、結果は散々でした。先行する類似野菜があまり良い販売実績を出していなかったのです。 (以下つづく)
| 読者の会 | ||
第17回 7月4日『農業経営者』読者の会 定例セミナーのご案内 (2008/07/01)
「必要なものを効率よく入れる施肥設計術」
【講師/関祐二氏 農業コンサルタント】
「土を調べて必要最低限の肥料を施す」——この基本技術を押さえているだろうか。土の中の成分を科学的に調べると、かなりの畑が尿素単肥や硝酸石灰の施用だけで健全で多収量になり、成分過剰害を抑えられる。この秋以降の肥料高騰を迎える前に、必要なものを効率よく入れる施肥設計を習得したい。

講師プロフィール
1953年静岡県生まれ。東京農業大学において実践的な土壌学に触れる。75年より農業を営む。営農を続けるなかで、実際の農業の現場において土壌・肥料の知識がいかに不足しているかを知り、民間にも実践的な農業技術を伝播すべく、84年より土壌・肥料を中心とした農業コンサルタントを開始。
場所: (株)農業技術通信社内セミナー会場
会費:一般参加の方は5,000円、『農業経営者』定期購読者の方は無料になります。
※ 今月号より、年間購読のお申込をいただいた場合も受講料は無料となります。

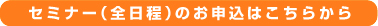
| 読者の会 | ||
第18回 7月16日『農業経営者』読者の会 定例セミナーのご案内 (2008/07/01)
「土地利用型から施設園芸へ〜シナジー効果のある複合経営の展開〜」
【講師/佐藤彰一氏(有)米シスト庄内 代表取締役社長(他、ゲスト農業経営者によるパネルディスカッション有)】
“自分の作ったものが誰に、どう食べられているか”を敏感に捕らえ、先駆けて高齢者マーケットに着目、お年寄りでも食べやすい玄米食品をヒットさせた(有)米シスト庄内。現在はコンテナ栽培の早出しブルーベリーなど、施設園芸にも展開中だ。「走る社長」佐藤氏が、シナジー効果のある複合経営を語る。

講師プロフィール
1954年山形県生まれ。95年米シスト庄内乾燥調整利用組合を設立。98年販売のための法人である(有)米シスト庄内を設立。庄内米の生産・加工・販売から始めて、「玄米主義 すっぴん煎」の生産・販売、ブルーベリーの生産・加工事業に取組む。現在の経営面積はコメ93ha、施設園芸1140坪。
パネリスト:宮川正和氏 (有)正八代表取締役(新潟県大潟村)
三輪民雄氏 (有)三輪農場代表取締役(群馬県前橋市)
関治男氏 (有)アクト農場代表取締役(茨城県茨城町)
日時:7/16(水)15:00〜18:00
場所:幕張メッセ国際会議場 中会議室303(JR京葉線・武蔵野線利用 海浜幕張駅より徒歩5分)
※アグロ・イノベーション2008同時期開催
会費:一般参加の方は5,000円、『農業経営者』定期購読者の方は無料になります。
※ 今月号より、年間購読のお申込をいただいた場合も受講料は無料となります。
協賛:AGCグリーンテック株式会社
後援:日本温室協議会

| 読者の会 | ||
第19回 8月8日『農業経営者』読者の会 定例セミナーのご案内 (2008/07/01)
「農場は人が創る〜農業でプライドをどう表現できるか〜」
【講師/永井進氏 ㈲永井農場 専務取締役 】
20歳で就農後、まず自主販売米のパッケージをデザインした永井氏。26歳で農場のコンセプトを形にした管理棟を建築。最近ではワイン文化の形成を意識したワインプロジェクト、小学校との稲作交流などの「農場づくり」から職業人の誇りを発信している。若手の「後継者」が挑む、新しい農場経営を語る。

講師プロフィール
1971年長野県生まれ。酪農学園大学短期大学卒業後、20歳で就農。長野県東御市で酪農と稲作の複合経営に取り組みながら、従来の大規模経営とは異なる農場発展の可能性を模索している。若手ならではの農場づくりを綴った「永井進の農場スタイルノート」を、本誌にて好評連載中。
場所: (株)農業技術通信社内セミナー会場
会費:一般参加の方は5,000円、『農業経営者』定期購読者の方は無料になります。
※ 今月号より、年間購読のお申込をいただいた場合も受講料は無料となります。

- ライスショック(大きな国で)
- 何がどうおいしいを数字ではっきりと(花総果菜)
- 農業起業講座。(ほぼ日刊三浦タカヒロ。)
- 広島で屋上緑化かるいちばんとカルベラの展示です♪♪♪(Urban Green Life 街にもっと緑を・・・ 兼定興産の屋上緑化土「かるいちばん」)